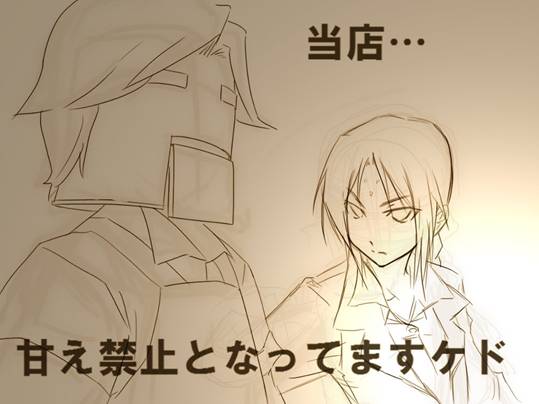|
最近善からぬ噂を耳にする事が増えた。
いわく「緋崎鈴芽は誰とでもやる尻軽女だ」と。
元々周囲からの評判がイマイチであった鈴芽だが、こうも悪意むき出しな悪評が囁かれるようになったのはつい最近になってからだ。
そもそも無口なガリ勉と言うイメージが定着しかけていた鈴芽に対して、その悪評はあまりに突飛であった。しかし噂とは恐ろしいもの。悪事千里を走るとでも言わんばかりの勢いで、鈴芽の悪評は校内に拡がっていった。
「鈴芽」
ある日の放課後、私は昇降口で彼女。緋崎鈴芽を呼び止めた。
昨日おとといと彼女は部活を休んでいた。といっても、毎日活動というわけでもなく、暇な時に部室に集まっては好き勝手に本やインターネットを見て資料を作成するというだけの部活である。たかが二日間来なかったというだけで彼女を咎めるのもおかしな話ではある。
勿論私もそんな事はどうだって良い。確かめねばならない事は別にある。
「何?」
いつも通り、素っ気ない様子で鈴芽は問い返す。反対に私はしどろもどろになりながら、おずおずと切り出した。
「えと……今日も何処かに出掛けるの?」
「ん。少しね」
「あの……あのね鈴芽。もし、もし言えたらで構わないんだけど。その……」
「?」
視線を合わせる事が出来ず、もじもじとしている私の様子に、鈴芽は僅かに小首をかしげる。しかしすぐに私の言わんとしている事を察したのだろう。俯いた私の脳天目掛けて、彼女のいたずらっぽい声が投げかけられた。
「暇なら行ってみる? 一緒に」
それは正に、小悪魔的倒置法であった。
シリーズ変態百合小説 「ランキングファイターズ編」
1
「ね、ねえ。どこに行くの?」
目の前をズンズンと突き進む鈴芽に、私は不安になってそう問いかけた。今更言う迄もないだろうが、私は鈴芽の誘いに抗う事が出来ずに、彼女の背中を追って早稲田通りを歩いているところであった。
「ブロードウェイ」
振り向きもせずに短くそう答え、鈴芽は迷いなくその足を進めた。
ブロードウェイとは恐らく、学校からほど近い所にあるショッピングセンター。中野ブロードウェイの事だろう。
もしや其処で男性と待ち合わせをして居るのだろうか? だとしたら、一緒に連れていかれた私はどうなってしまうのだろう?
様々な考えが頭の中を駆け巡り、耳から蒸気を吹き出しそうな感覚さえしてくる始末だ。誰か助けて。
「例の噂を気にしてるんだろう?」
そんな私の様子に気付いてか、投げかけられた鈴芽の声音は優しいものだった。
「え? ああ、まあ……うん」
相変わらずのしどろもどろさで、しかし私は素直に頷く。
「で、でもね。私はあんな噂なんて信じてないわよ! 鈴芽の事をちゃんと見てれば、あんなのただの言いがかりだってすぐに分かるもの!」
「ふふ、まあ私のキャラじゃないよな」
私の言葉に、鈴芽も肩を揺らして笑った。その通り、あんな噂、鈴芽のキャラクターからはかけ離れて居るのだ。
鈴芽の反応で確信を深めた私は、それ迄の陰鬱な気持ちが嘘のように、この晴れ渡った青空のように爽やかな気分に包まれた。
のだが……
「でもまあ、ある意味間違ってもいないけどね」
「……はい?」
晴れ渡った心に稲妻が落ちる。痺れた心はその動きを停止し、ただの一声を発するのにすら随分と時間がかかってしまった。
気付けば、何時の間にやら入館していた中野ブロードウェイのエレベーターホールにて、侵入を促すかの如く大口を開けたエレベーターが、私達の目の前に鎮座していた。
2
中野ブロードウェイ四階のエレベーターホールに足を踏み出した私の目に飛び込んできたのは、通路の向こう側に屯す人々の群れだった。
一体何のコーナーなのだろう? あまりブロードウェイに足を運ぶ事がなかった私には、店内の配置が掴めて居なかった。
「何の集まりなの?」
見ればその人垣のほぼ全てが男性で構成されているではないか。まさかこの人数を相手に……?
悪寒にも似た感覚に襲われながら、私は恐る恐る鈴芽に尋ねる。対する鈴芽の反応は、やはりと言うかなんと言うか、あっけらかんとした調子の言葉だった。
「ゲームの……そういえば今日は大会だった」
忘れていたと言わんばかりに、鈴芽は腕時計に目を遣る。彼女の時計は日付表示付きのちょっと良いやつだ。
ふむと小さく呟くと、鈴芽はちらりと私の方に視線をやり、駄目元と言う風にこう言った。
「やっぱりゲームライノじゃダメ?」
「一体何処まで連れ回すつもりなのよ」
笑いながら返したつもりではあった。ただ、鈴芽の反応からは「苦」の字がつく笑顔にしかなっていなかった事が伝わって来た。
3
一言でいうならば、そこはスーパーのゲームコーナーをちょっと大きくしただけのような区画であった。
エレベーターホールから通路を挟んで真正面にある其処は、数台のビデオゲームの筐体がずらりと並べられており、ゲームセンターの一角だけが突如として現れたかのようにも見える。
並んでいるゲームは、どれもこれも対戦格闘ゲームという、およそ女子とは縁遠いものばかりである。
「鈴芽、ここで何かあるの?」
鈴芽がゲーム好きである事は知っていたが、流石に男性に混じって格闘ゲームは無いだろう。そう思って一応聞いてみると、鈴芽は両替機に千円冊を投入しつつ、答えになっているのか居ないのか、少なくとも私にはよく分からない返事を返してきた。
「水曜だから大会があるけど……何時からだっけ?」
「えっ?」
突然質問で返された。大会があるらしいという事は今さっき鈴芽の口から聞いたばかりだったが、何の大会かも分からない私に開会時間など分かるはずも無かった。それ以前に私の質問はそういう意味じゃあない。
困るばかりの私を他所に、鈴芽の質問に対する答えは直ぐに返ってきた。
「おぉ、スズメじゃん! 大会は九時からだよ。なに? 参加すんの?」
「しない、聞いただけ」
それはたまたま通りかかっただけと思しき、ゲームコーナーのスタッフらしき男性だった。
男性スタッフは鈴芽の姿を認めるや、嬉しそうに答え、対する鈴芽は素っ気なく返した。
「し、知り合い?」
「ただの店員」
「いや、それは分かるんだけど……」
正直、鈴芽が男性と言葉を交わしている所を、私は初めて目の当たりにした。
普通に考えれば、漫画やアニメの世界に生きる少女ではないのだから「男性と話をした事ありません」なんて事は無くて当然なのだが、それでも初めて見る彼女の新たな一面に驚きと、そしてほんの少しだけのショックを感じずには居られなかった。
4
鈴芽が筐体に着いてから数分。画面内で展開されている事が全く理解出来ない私を差し置いて、鈴芽は静かに。そして周囲はうるさく盛り上がっていた。
鈴芽は少しプレイしては席を立ち、また少ししては席に着くという感じで対戦を続けていた。
格闘ゲームはこう言うプレイスタイルが主流なのか、せいぜいクレーンゲーム程度しかした事がない私には分からなかったが、鈴芽が相当勝ち進んでいた事は確かだった。
次第にプレイの順番待ちをしていた客の多くが、彼女のプレイを観戦しようと周りを取り囲むようになり、隣で見ているだけの私は大層肩身が狭く感じた。
時折通過する台車に道を譲るよう声がかけられた際、みんなでさっと端に寄る瞬間だけが一息つけるタイミングだ。
「準備出来たー? じゃあスズメこっち来てー」
先程から何やら筐体をいじっていた店員が、マイクで鈴芽の名を呼んだ。撮影がどうのと言っていたが、一体何が起こると言うのだろう?
『OK? じゃあ大会前の特別試合始めるねー。』
マイクを持った店員が突然そんなアナウンスを入れる。鈴芽は筐体に向かいながら首だけ振り返り確認する。
「これって奢りで良いんだよね?」
『スズメの動画上げろってあちこちでうるさいんだよね。だから今日だけ店の奢りで。ってか段位戦でろよ。いつまでモヒカンやってんだテメー!』
「じゃあ一時間早く開催してよ」
「当店、甘え禁止となってますケド」
「それ気に入ったの?」
鈴芽のぼやきに答えたのは、マイクを持った店員ではなく筐体の向かいに座った店員だ。店員がゲームするゲームセンターなんて始めてみたわ。
マイクを握った店員を始め、会場の空気はどんとん熱気を増してゆく。正直、私には全く状況が掴めなかったが、その場の誰もが鈴芽のプレイを観戦したいと思っている事が、筐体を取り囲んだ人垣の分厚さからも見て取る事が出来た。
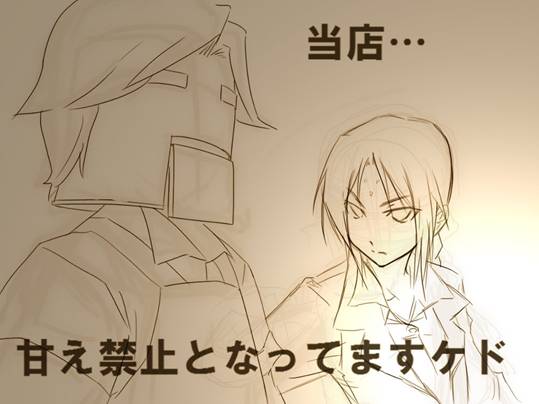
5
結論から言うと、確かに鈴芽は多くの男性と取っ替え引っ換え闘(や)っていた。
その実力は素人の私から見ても凄まじく、周囲のプレイヤー達からも賞賛を浴びるほどであった。
普段の学校生活では見られない、男性にちやほやされる鈴芽を見るのは何となく釈然としない感じもしたが、万年女日照りっぽいあんな場所に屯している連中から見れば、同じ趣味を持った女性……しかもとびきりの美少女が輪に入って来たならば、ちやほやしない方が不自然なのかもしれない。
そして鈴芽が格闘ゲームプレイヤー達の間で評判になり始めたのは割と最近の事であったそうで、それまではちょくちょく顔を出す女の子程度の認識でしかなかったそうだが、ここ数ヶ月で信じられないほどの実力を身につけ、女性初の修羅入りを果たしたそうだ。
言っている意味は分からなかったが、兎に角鈴芽が凄かったと言う事なのだろう。
また、その頃からネット上でも格闘ゲームプレイヤースズメの名が出回り始めたらしく、それが校内の格闘ゲームプレイヤーである男子生徒達にも知れ渡ったのだ。
以前鈴芽が「最近妙に男子が絡んでくる」とウザそうに語っていた。その時は珍しく自分はもてますアピールでも始めたのかと思ったが、恐らくは此方の関係で女子と繋がりを持とうとした浅はかな男子が鈴芽にアプローチを仕掛けただけのようだ。
情報がインターネット経由であると言うのも、普段調べものにしかパソコンを使わない鈴芽自身に心当たりが無かった一因だろう。
その辺りが原因となり、グループ外の女子である鈴芽が突然もて始めた事を快く思わない女子グループが陰湿な嫌がらせを行ったというのが、恐らく昨今の噂話の真相だ。
女の嫉妬心の、何と恐ろしい事か……
6
その後の経過だが、鈴芽に関する評判も一時の流行り病が如く、二週間もすれば何処かへ消え去ってしまった。
先日対戦した店員(その業界では超有名なプレイヤーだったらしい)との試合がネット上で公開されてから、格闘ゲーマースズメの名が爆発的に広まった事に加え、鈴芽本人が例のデマに対してあまりにも無反応すぎた為、言っている方が折れてしまったのだ。
「ねえ鈴芽」
「うん?」
「格闘ゲームってどこが面白いの?」
「うーん、誰とでも対等に勝負出来る所かな?」
「性別とか関係なしにってこと?」
「それもあるし……それ以外の所でもある」
「それ以外の?」
珍しい鈴芽が真剣に考える素振りを見せながら答えたので、私は思わずその話題を継続した。
「例えば身体的能力とかさ、ああいうゲームならある程度迄の上限がどうしても出て来るから、後はそれ以外の読みとかが重要になってくるじゃん?」
「いや、其処までは分からないんだけどね」
「そう言うジャンルなら、どっちが卑怯とか言われずに対等に戦えるだろう? 其処が良いんだよ」
自分の答えに満足がいったのだろうか? 鈴芽はわずかに頬を緩めながら、そうキッパリと言い切った。
その微笑を前に、思わず聞き流してしまいそうになったが、何やら深読みできそうな言葉である。
(よし、二学期はその辺りを掘り下げて行こう!)
先の楽しみも出来た所で、私は手元の資料に視線を落とした。
再来週まで迫った文化祭の出し物である報告書は未だ完成のめどが立たず、こうやって笑って居られる場合ではないのだが……
(まあいいか、鈴芽は可愛いし。まだ二週間あるから頑張れば!)
夏の暑さも盛りを過ぎ、いよいよ私達二人で迎える最初の秋が訪れようとしている。
今はただ、夏の陽射しに浮かび上がる鈴芽のシルエットに欲情しながら、じきに終わりを告げるその絶景をこの目に焼き付けようと、私はひたすら目を凝らし、彼女を見つめ続けていた。
おわり
|